目次
料理教室に開業届は必要?まず知っておきたい基礎知識
自宅で料理教室をやってみたい」
「でも、開業届って必要なの?」
そんな疑問を持って検索しているあなたへ――
料理教室を開業するときに、多くの方が迷うのが「開業届を出すかどうか」。
特に、自宅で少人数・知り合い相手に教える場合や、副業で始める場合は判断が難しいですよね。
そもそも開業届とは?
「開業届(正式名:個人事業の開業・廃業等届出書)」は、
“私は個人事業主として仕事を始めます”と税務署に申告する書類です。
この書類を提出することで、あなたの活動は「事業」として税務上も認められるようになります。
対象は、以下のような収益活動です:
・自宅で料理を教えてお金をもらう
・レンタルスペースでレッスンを開催する
・オンラインで受講料を受け取る
つまり、「お金をもらって継続的に料理を教える」なら、原則として提出すべきというのが国税庁のスタンスです。
提出しないと違法になるの?
いいえ、「出さなかったから罰せられる」というものではありません。
ただし、以下のようなリスクが出てきます。
・青色申告ができない(節税できない)
・収入が増えてきたときに慌てて対応することになる
・扶養や住民税の申告で整合性がとれなくなる
開業届を出す=「責任が重くなる」と感じる人もいますが、きちんと準備することで“安心して続けられる”状態になるというのが実際です。

どんな人が対象になるの?
税務署では、「継続的に収益を得る意志がある活動」を“事業”とみなします。
つまり、こんなケースは提出対象になります:
・月に1〜2回の料理教室でも、受講料をいただいている
・インスタから申し込みが来て、知らない人にも教えている
・モニター価格で始めたが、今後も教えるつもりでいる
逆に、以下のような場合は提出が不要なこともあります:
・まったく報酬をもらっていない(完全ボランティア)
・1回きりの単発で、継続する予定もない
▶︎ 「趣味の延長」か「事業としての意思があるか」が判断の分かれ目です。
開業届を出すメリット・デメリット
「とりあえず提出しないで始めてみようかな」
「扶養に影響あるって聞いたけど、本当?」
そんな迷いを持つ方のために、ここでは料理教室という働き方ならではの“開業届のメリット・デメリット”を具体的にお伝えします。
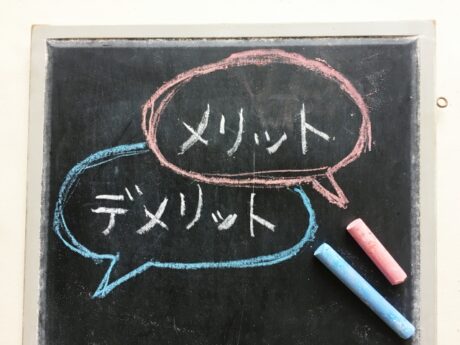
【メリット①】青色申告ができる(節税)
開業届を出すことで、確定申告の際に「青色申告」が選べるようになります。
青色申告にすると、次のような節税メリットがあります。
・65万円の特別控除が受けられる(電子申告+複式簿記)
・赤字を3年間繰り越せる(初年度の赤字を翌年以降に使える)
・家事按分(自宅の一部を教室として使う場合、家賃や光熱費を一部経費にできる)
▶︎これは収入が少ないうちから意識しておくと、後々とても助かります。

【メリット②】“事業者”として信用がつく
開業届を出すと、「屋号付きの口座が作れる」「仕事としての自覚が持てる」など、教室運営への“本気度”が形になります。
また、こんな場面で「開業していて良かった」と感じる人も多いです。
・補助金や助成金に応募したいとき
・講師としての仕事依頼が来たとき(行政・企業案件)
・ビジネス口座、事業用クレカをつくりたいとき
▶︎自分にとっても、周りにとっても「仕事」としての信頼感が生まれます。
【デメリット①】扶養や保険への影響がある
ここが最も気になる人が多いポイントです。
開業届を出しただけでは扶養は外れませんが、「事業所得が増えて、年間の所得基準を超える」と、扶養から外れる可能性があります。
例:
・配偶者控除:年間所得48万円を超えると対象外
・配偶者特別控除:年間150万円以内なら一部適用可能
・健康保険の扶養基準:年間130万円以上で外れる場合も
▶︎ 開業=即扶養から外れる、ではなく、「所得の金額」が判断基準です。
【デメリット②】確定申告・帳簿管理が必要になる
事業主になると、年1回の確定申告が必要になります。
また、帳簿の記帳(売上・経費の管理)も行う必要があります。
ただし、最近は会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)で初心者でも簡単にできるようになっています。
▶︎ むしろ最初から整えておくことで、「利益が出てきたときに慌てない」自分になれます。

▼まとめ:出す=リスクではなく、整えるチャンス
開業届は、「出すべきか悩む書類」ではなく、
“これから仕事として本気で取り組んでいく”ための第一歩だと思ってください。
副業レベル・小規模でも、「いつか本業にしたい」と思っている方には、むしろメリットが多い制度です。
料理教室での開業届、提出のタイミングと出し方
「出したほうが良さそうなのは分かった。でも、いつ出すべき?どこで?どうやって?」
そんな疑問にお答えします。
この章では、料理教室を始める人向けに、現実的なタイミングと具体的な提出方法をわかりやすく整理しました。
【いつ出すべき?】タイミングは“最初の収入が出る前後”
開業届は、「事業を始めた日から1ヶ月以内に出す」と国税庁のページには書かれています。
が、実際は以下のように判断してOKです。
|
状況
|
出すタイミングの目安
|
|---|---|
|
教室の準備を始めたばかり
|
まだ不要(売上が出る前なら)
|
|
初めてお金をいただいた
|
出すタイミング。1ヶ月以内が推奨
|
|
モニター価格で教えている
|
継続意思があるなら、出す準備を
|
▶︎ 実際には、「最初の申込があった時点」で提出するのがスムーズです。
【どこで出す?】税務署に出します
提出先は、自宅住所を管轄する税務署です。
Webで「◯◯市 税務署 開業届」で検索すればすぐ出てきます。

【どうやって出す?】提出方法は3つ
・税務署の窓口に持参(印鑑と身分証を持参)
・郵送(控えにも切手を貼って同封すると、返送してもらえます)
・e-Tax(電子申告)(マイナンバーカードとカードリーダーまたはアプリが必要)
▶︎ 初心者には「税務署に持っていく」か「郵送」が一番確実で安心です。
【必要な書類】開業届+本人確認
・個人事業の開業・廃業等届出書(A4・1枚)
→ 国税庁HPからダウンロード or 税務署に用紙あり
・本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)
・控え用のコピー(提出用と一緒に2部持っていく)
【書き方のポイント】屋号や業種はどう書く?
・屋号(教室名):なしでも可。決まっていれば書いてOK
・職業:「料理教室講師」「料理講師」「料理指導業」など
・届出の理由:「新たに事業を開始」など、該当項目に○を記入
書き方で不安がある場合は、税務署に電話すれば丁寧に教えてくれます。
注意
▼忘れず一緒に出すといいもの
「青色申告承認申請書」(別紙)を一緒に出すと、節税効果が最大になります。
これを出しておかないと、白色申告になってしまい損をする可能性も。
▶︎ 「開業届」と「青色申告承認申請書」はセットで提出するのが鉄則!
開業届を出すことは、事業主としての“スイッチ”を入れるようなもの。
緊張するかもしれませんが、1度出してしまえば「思っていたより簡単だった」と言う人がほとんどです。
自宅で少人数なら開業届は不要?よくある誤解を解説
「自宅で、月に1〜2回だけだし…」
「知り合いしか来ないし、お金もそんなに取ってないし…」
だから“開業届はいらない”と思っていませんか?
実はその考え、誤解されがちなポイントです。
ここでは、「どこまでが“趣味”で、どこからが“事業”なのか」明確にしていきます。

【結論】利益が発生していて、継続の意思があるなら提出対象
国税庁の判断基準はシンプルです。
「収入を得る目的で、継続的に活動しているかどうか」
つまり、次のような状態であれば、規模の大小に関わらず原則として開業届の提出が必要です。
・月に1回でも受講料をもらっている
・知り合いだけでなく、SNSやブログから新規も集客している
・続ける意思があり、今後も開催予定がある
【OK例】開業届が“不要”なパターン
・友人に一度だけ料理を教え、お礼としてお菓子をもらっただけ
・趣味の延長で無料レッスンのみを実施している
・年に1回のお楽しみイベントで、利益も出ていない
これらは「事業としての継続性・収益性がない」ため、提出不要のケースに該当します。
【NG例】開業届を出すべきなのに、出していないケース
・モニター価格とはいえ、何度も有料で開催している
・SNSで広く集客しており、実際に申し込みが来ている
・「今は副業だけど、将来は本業にしたい」と思っている
このような場合、税務署から見れば“事業”とみなされる可能性が高くなります。

「少人数だから大丈夫」は税務上の判断基準ではない
よくある勘違いが、「規模が小さいから開業届は不要」という考え。
たとえ生徒が1人でも、毎月開催していて、報酬を受け取っていれば“ビジネス”と見なされます。
むしろ、初期の段階からちゃんと届け出をしておくことで、以下のようなトラブルを避けられます。
・売上が増えたときに遡って申告が必要になる
・扶養・確定申告で整合性が取れなくなる
・「無申告」であることが周囲に知られる(補助金・仕事依頼などで)
▼現実的なアドバイス
「いきなり本格的に開業なんて不安…」
そう思うなら、モニター開催で“無料または材料費のみ”で試してみるという方法もあります。
ただし、すでに“お金をいただいて教えている”なら、今から開業届を出しても全然遅くありません。
小さく始めること=軽くやっていい、ということではありません。
少人数だからこそ、丁寧に準備をして、安心して育てていける教室にしていきましょう。
開業届と一緒にやっておくと後悔しないこと
「開業届を出して個人事業主になった!」
これでひと安心…と思いきや、実はこのタイミングで“やっておくと後々ラクになること”がいくつかあります。
ここでは、料理教室のような個人での小さなビジネスを始める方にとって、“やっておくと信頼感が増す&仕事が回りやすくなる”ポイントをまとめました。
【1】屋号(教室名)をしっかり決めておく
開業届には「屋号(事業名)」を記入する欄があります。ここは未記入でもOKですが、しっかり決めておくとこんなメリットがあります。
・SNSやブログに一貫性が出て、信頼されやすくなる
・屋号入りの銀行口座が作れる(例:「〇〇料理教室」名義)
・補助金やセミナー講師依頼時に「事業名」で活動できる
▶︎ おすすめは、「料理教室名+英語 or 和風テイスト+あなたらしさ」を組み合わせたもの。
(例:おうち発酵ごはん教室『Hibi』/季節のごはん教室『なごみ舎』など)
【2】事業専用の銀行口座を開設する
開業したばかりの方によくあるのが、「プライベートと事業のお金がごちゃまぜ」問題。
これ、のちのち確定申告や経費管理が本当に面倒になります。
できればこのタイミングで、事業専用の銀行口座(ネット銀行でもOK)をひとつ作っておくのがおすすめです。
▶︎ 屋号付きの名義にできる銀行なら、「教室としての信用」もUPします。
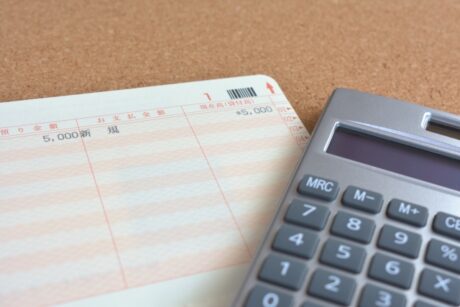
【3】SNS・ホームページ・ブログも“屋号”で統一を
せっかく屋号を決めたら、InstagramやLINE公式アカウント、ホームページなども名称を統一しましょう。
・名前がバラバラだと信頼されづらい
・名刺や講座資料の印象も弱くなる
・Google検索で教室名が出てきやすくなる(SEOにも強い!)
▶︎ SNS発信がこれからの集客において“土台”になるため、発信の世界観=ブランドの始まりと考えて行動すると◎。
【4】名刺・請求書テンプレート・講座資料の準備
屋号やロゴが決まったら、名刺・請求書テンプレート・講座案内資料(PDF)などもこのタイミングで作っておくと、いざというときスムーズです。
▶︎ たとえば、イベント出展、コラボ開催、取材などが急に来たとき、「ちゃんとしてる教室だな」と思ってもらえます。

▼まとめ:開業届=ゴールではなく、ブランドの“スタート地点”
開業届を出したという事実よりも、そのあとに「どう見せていくか」「どう伝えていくか」で教室の未来は大きく変わります。
ほんの少しの準備で、信頼感も、自分自身のモチベーションも、グッと上がりますよ。
まとめ|開業届は「届け出」ではなく、自分に“旗を立てる行為”
料理教室の開業を考えたとき、開業届は“書類上の手続き”にすぎないように思えます。
でも実際には、「私はこの道で生きていく」という、未来への宣言でもあります。

▼ここまでのまとめ
・開業届は、事業としての活動を税務署に届けるための書類
・料理教室が“仕事”として動き始めたら、提出が必要になる
・扶養や確定申告との関係を事前に知っておくことで、後から困らない
・自宅で少人数でも、継続+収益があれば対象になる可能性が高い
・屋号・口座・発信の統一が、信頼感と集客力を高めてくれる
「まだ開業ってほどじゃないから…」
「こんな自分に、開業なんて言葉は大げさじゃないか…」
そう感じている方こそ、“開業届”を出すことが、人生の流れを変えるきっかけになることもあります。
▼もし、今あなたがこんなことで悩んでいたら…
・扶養のことが心配で、一歩を踏み出せない
・開業届って本当に自分に必要?とモヤモヤしている
・資格も実績もないけど、教室を仕事にしたい
・本業にするにはどう進めていいか分からない
その悩み、ひとりで抱え込まずに相談してみませんか?
🔹あなたらしい教室の始め方を、一緒に見つける相談会
僕はこれまで、ゼロから料理教室を始めた女性たちが“仕事”として軌道に乗せるお手伝いをしてきました。
「開業届を出したあと、どう進めればいいのか?」
「そもそも、出すべきなのか?」
そんな段階の方にも、具体的なステップを一緒に整理する【個別相談会】を実施しています。

▶︎ 詳細・お申し込みはこちら:
【薄利多売から抜け出し、あなたらしい高単価料理教室を叶えるプラン作りセッション】
👉個別相談階はこちらから
🔹もっと学びたい方へ|無料メルマガで最新情報をお届け中
「料理教室って、実際どうやって収益化するの?」
「SNSやブログでどうやってファンを作るの?」
「レシピで教えない料理教室って何?」
そんなテーマを、無料のメルマガで深掘りして発信しています。
▶︎ メルマガ登録はこちら:
👉無料メルマガ登録はこちらから
▼最後に
開業届は、ただの1枚の紙かもしれません。
でもその1枚が、「私、やるんだ」というスイッチになります。
あなたの想いを、誰かの喜びにつなげる教室へ。
その第一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。
応援しています。